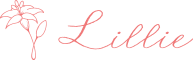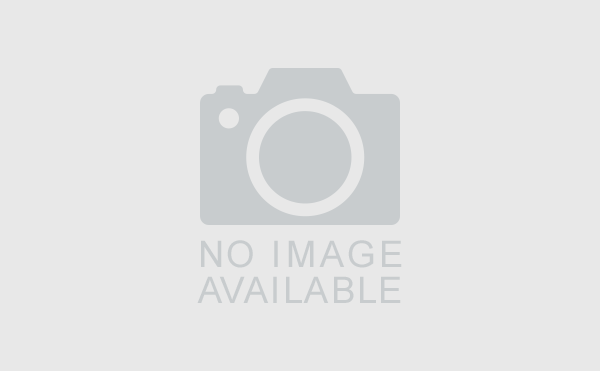行政書士による「通知書」作成依頼の解説:誰の名前で出す?署名・押印のルールとは
行政書士は、法律で定められた書類作成の専門家です。特に、内容証明郵便や契約書、告訴状といった法的文書を作成する際、「行政書士がどこまで関与するか」によって、書類の形式や署名・押印のルールが変わってきます。
依頼者様が不安なく書類を提出できるよう、行政書士の関与の形式と、それに伴う法的・実務的な取り扱いについて解説します。
1. 行政書士の業務範囲と「代理」の限界
まず、大前提として知っておくべきことは、行政書士の業務は「書類作成の代理」と「提出手続きの代理」が中心であり、「法律事務の代理」は弁護士法により禁じられている点です。
具体的には、行政書士は依頼者の代理人として相手方と交渉したり、裁判所へ出廷したりすることはできません。
この業務範囲の違いが、書類への記名・押印のルールに反映されます。
2. 書類作成における関与の3つのパターン
行政書士が通知書や契約書などの書類を作成する際の関与の仕方は、主に以下の3つのパターンに分けられます。
パターンA:本人名義で作成する通知書等の「代書」
これは、行政書士が依頼者本人の意思に基づき、その内容を正確に筆記代行する形式です。
- 関与の形式: 「代書」は、本人の意思に基づく単なる筆記代行である。
- 書類の名義: 依頼者本人の名義(例:佐藤富彦)で作成・提出される。
- 行政書士の記名・押印: 不要。
実務上は、行政書士の名前や職印を入れず、あくまで依頼者本人が作成した書類として扱われます。これにより、相手方との直接的な法的紛争の代理人であるという誤解を防ぎます。
パターンB:行政書士が「代理人」として作成・提出する場合
これは、行政書士が法律で認められた「官公署に提出する書類」について、依頼者に代わって作成し、提出手続きも代行する場合です。
- 関与の形式: 代理行為を伴う行政書士業務として実施される。
- 書類の名義: 依頼者名義だが、行政書士が代行したことを明示する。
- 行政書士の記名・押印: 必要。
たとえば、許認可申請書など、官公署に提出する書類に行政書士が関与したことを明示するために、記名と職印の押印が義務付けられています。
パターンC:添付書類として関与を明示したい場合(任意)
パターンAの通知書であっても、「この書類は専門家が作成しました」という権威付けのために、行政書士が関与したことを明示したい場合があります。
- 関与の形式: 依頼者からの要請により、作成者として明示する。
- 書類への記載: 通知書とは別に、「本書は行政書士〇〇が作成しました」といった添付書類や奥書という形で記載されます。
- 行政書士の記名・押印: 任意。
この記載自体に法的交渉の代理権が発生するわけではありませんが、相手方に対し「本件は専門家が法的な視点に基づいて整理している」というメッセージを伝える効果があります。
3. まとめ:内容証明作成における実務上の取り扱い
内容証明郵便などの紛争性のある通知書を作成する場合、行政書士は通常、「パターンA:本人名義の代書」の形式で作成します。
これは、行政書士が交渉や訴訟といった「法律事務の代理」をしていると誤認されるのを避けるためです。
内容証明作成時の署名・押印のルール
- 誰の名前で出すか: 依頼者本人名義(相手方への意思表示を明確にするため)。
- 誰が署名・押印するか: 依頼者本人が署名(行政書士の記名・押印はしないことが多い)。
- 行政書士の関与: 法的交渉の代理人ではないことを示しつつ、裏面等に作成者として記載する場合がある。
ご依頼の際は、行政書士が「あなたの味方として適切な書類を作成してくれる」のであって、「あなたの代理人として交渉してくれる」わけではない、という点を理解しておきましょう。
*本記事に記載の見解は場合によって変わり得ることがあるため、必ず最新情報を確認してください